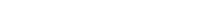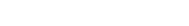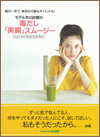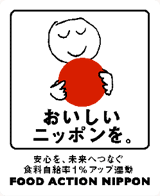人を幸せにする器を創る、練り込み技法 一ツ葉焼の物語
人を幸せにする器を創る、練り込み技法 一ツ葉焼の物語
陶芸家 : 北原不二雄さん
場所 : 宮崎県国富町深年
日本の陶芸家の約1%でしか作られていない独自の練り込み技法を使い、幸せと言う名の陶器を作る「北原さん」。
その独自の制法と、技術について伺ってきました。
一ツ葉焼とは~1%の匠の技~
一ツ葉焼きの技法「練り込み技法」とは、 約1200年前(中国・唐時代)に考案され数種類の粘土を組み合わせ、土の違いだけで模様を作りだす独自の技術を指す。非常に高度な技術を要する為、通常はしま模様・市松・渦巻きなどのシンプルな柄が代表的な模様となっている中、一ツ葉焼きの様に動物や花柄などの絵柄を創り出す技術は、非常に珍しく日本にいる陶芸家の約1%にしか作られない匠の技となってしまっている。
例えば、お皿の模様となる花。花びらになる粘土を一つ一つ細く伸ばして合わせていく。

 さらに花びらと花弁になる芯のパーツを組み合わせていき、花びら全体を仕上げていく。
さらに花びらと花弁になる芯のパーツを組み合わせていき、花びら全体を仕上げていく。

 そして、いくつもの花びらが練り込まれる。
そして、いくつもの花びらが練り込まれる。

 粘土自体に模様を作り、器などの形に仕上げていくその工程は、他の手法と比べると何倍もの根気のいる仕事だ。
粘土自体に模様を作り、器などの形に仕上げていくその工程は、他の手法と比べると何倍もの根気のいる仕事だ。
目の前で花びらのパーツを作って見せてくれる北原さんに、どうしてこの方法で陶器を作り始めたのか尋ねると、「あまり作る人がいなかったから(笑)」とあっさりとにこやかに笑って答え、話を始めてくれた。
「16歳の頃に愛知県の瀬戸市に移り、陶芸の道に入った。もともと絵を描いたり芸術的なことが好きやったから、自然とやきものの道にね。」
例えば、お皿の模様となる花。花びらになる粘土を一つ一つ細く伸ばして合わせていく。
目の前で花びらのパーツを作って見せてくれる北原さんに、どうしてこの方法で陶器を作り始めたのか尋ねると、「あまり作る人がいなかったから(笑)」とあっさりとにこやかに笑って答え、話を始めてくれた。
「16歳の頃に愛知県の瀬戸市に移り、陶芸の道に入った。もともと絵を描いたり芸術的なことが好きやったから、自然とやきものの道にね。」
幸せと言う名の陶器
昔の宮崎には焼物が無く空白地帯だったそうで、瀬戸で15年学んだ後宮崎に戻り、最初の窯元を開いたのは昭和53年の事だった。幸福を呼ぶ松の一つ葉の名前から『一ツ葉焼』と名づけ、宮崎に帰って約30年、その名に負けない作品を次々と発表し、その作品で多くの人達を笑顔にし、宮崎県知事賞や匠の表彰など数々の賞を受賞した。
何十年もの間、粘土を練り、動かしている北原さんの手。その手が巧みに、粘土を立体的に組み合わせ、花や動物を形作ってく。想いもしない模様が生まれてくるその手に釘付けになっていると、北原さんは言う。
何十年もの間、粘土を練り、動かしている北原さんの手。その手が巧みに、粘土を立体的に組み合わせ、花や動物を形作ってく。想いもしない模様が生まれてくるその手に釘付けになっていると、北原さんは言う。
器を手に取る人達に楽しんでもらいたい
お仕事をされる上でストレスとか溜まらないんですか?という質問に、「それがね、ぼくは病気なんです。陶芸病ってやつです(笑)。 自分の好きな事だから。用事で外に出かけて行っても、帰った後は必ず20分でも30分でも土を触って眠る。」いつも笑顔の北原さんにとって、土は北原さんの一部なのかもしれない。「自分も楽しみたいし、一つ葉焼きの器を手に取るみなさんにも楽しんでもらいたい。それが僕のモットーです。」
次世代にも届けたい ~幸福の器と匠の技~
「この練りこみ技法で作る陶芸家は、日本にいる陶芸家のうち約1%。昔からある技法やっちゃけど、ほとんどその作り方を世間に出していない。」
「継承が今まであまり無くて自分が苦労した部分もあったから。だからできるだけ、弟子や子供達にもこの技法を伝えて・広めていきたいです。このままだと、いずれ消えてしまうかもしれない技法だから・・・・やっぱりずっと残していきたい。」
そう語る北原さんの頭の中と手の中には、今日もまた、新しいパーツが組み立てられていく。
一つ一つ土と、器と話しながら、出来るだけ多くの人達に笑顔と幸せを届けるために。
安心の物語
|